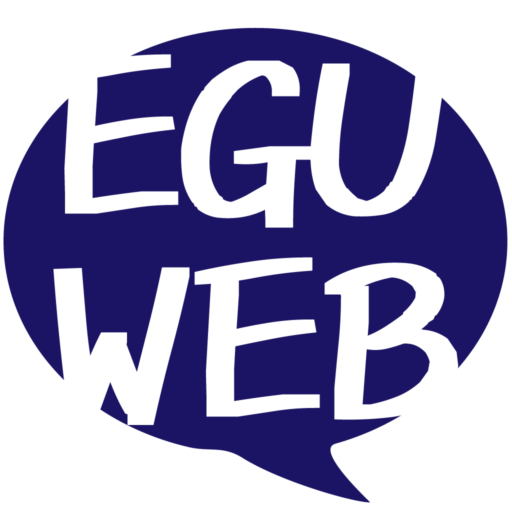【経営指標一覧】経営の主要キーワード・ビジネスで使える財務用語まとめ

この記事は約4分で読めます。
経営指標一覧をまとめています。※随時追加していきます。
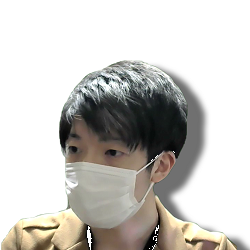
このページをブックマークしておくと便利です!
記事一覧ページはこちら▼

Finance(財務・経営)
保存版/経営指標一覧【経営の主要キーワード一覧】 【経営指標一覧】経営の主要キーワード・ビジネスで使える財務用語まとめ経営指標一覧をまとめています。※随時追加していきます。 このページをブックマークしておくと便利です! 記事一覧ページはこち...
経営指標一覧
経営指標で使われる主なキーワードの一覧です。
※別タブで開く場合はCtrlキーを押したままクリック、同じページで切り替える場合はそのままクリックください。
- BSC(バランスト・スコアカード)
- CAGR(年平均成長率)
- CCC(Cash Conversion Cycle)
- D/Eレシオ(ディーイーレシオ)
- DCF法(割引キャッシュフロー法)
- EPS(イーピーエス)/1株当たり純利益
- EBIT(イービット)/利払税引前利益
- EBITDA(イービットディーエー)
- EV/EBITDA倍率(イーブイ・イービットディーエーバイリツ)
- EVA(経済的付加価値)
- IRR法(あいあーるあーるほう)/内部収益率法
- NPV法(正味現在価値法)
- ROE(アールオーイー)/自己資本利益率
- ROA(アールオーエー)/総資産利益率
- ROIC(投下資本利益率)/(とうかしほんりえきりつ)
- WACC(加重平均資本コスト)/(かじゅうへいきんしほんこすと)
- アルトマンのZ値
- インスタントカバレッジ
- う)売上高(うりあげだか)
- う)売上原価(うりあげげんか)
- う)売上原価率(うりあげげんかりつ)
- う)売上高成長率(うりあげだかせいりょうりつ)
- う)売上原価率(うりあげげんかりつ)
- う)売上高営業利益率(うりあげだかえいぎょうりえきりつ)
- う)売上高経常利益(うりあげだかけいじょうりえきりつ)
- う)売上増加率(うりあげぞうかりつ)
- う)売上高販管費率(うりあげだかはんかんひりつ)
- う)売上高総利益率(うりあげだかそうりえきりつ)
- う)運転資本比率(うんてんしほんひりつ)
- え)営業利益
- え)永久成長率モデル
- か)株主資本比率(かぶぬししほんひりつ)
- か)ギアリング比率
- か)キャッシュフローマージン
- き)キャッシュフロー計算書(C/F)
- け)経常利益(けいじょうりえき)
- げ)限界利益(げんかいりえき)
- げ)限界利益率(げんかいりえきりつ)
- げ)現金預金比率(げんきんよきんひりつ)
- げ)現預金借入金比率(げんよきんかりいれきんひりつ)
- こ)固定資産(こていしさん)
- こ)固定負債(こていふさい)
- こ)固定負債比率(こていふさいひりつ)
- こ)固定比率(こていひりつ)
- こ)固定資産構成比率(こていしさんこうせいひりつ)
- こ)固定長期適合率(こていちょうきてきごうりつ)
- ざ)財務レバレッジ(ざいむればれっじ)
- ざ)財産価値(ざいさんかち)
- じ)自己資本比率(じこしほんひりつ)
- じ)自己資本当期利益率(じこしほんとうきりえきりつ)
- し)資産回転率(しさんかいてんりつ)
- し)資本生産性(しほんせいさんせい)
- し)正味運転資本(しょうみうんてんしほん)
- じ)純資産増加率(じゅんしさんぞうかりつ)
- じ)純手元資金(じゅんてもとしきん)
- そ)損益計算書(P/L)(そんえきけいさんしょ)
- そ)損益分岐点(そんえきぶんきてん)
- そ)損益分岐点比率(そんえきぶんきてんひりつ)
- そ)総資本経常利益率(そうしほんけいじょうりえきりつ)
- そ)総資産成長率(そうしさんせいちょうりつ)
- そ)総資本回転率(そうしほんかいてんりつ)
- た)棚卸資産回転月数(たなおろししさんかいてんげっすう)
- た)棚卸資産構成比率(たなおろししさんこうせいひりつ)
- た)単純回収期間法(たんじゅんかいしゅうきかんほう)
- た)貸借対照表(B/S)(たいしゃくたいしょうひょう)
- で)デュポン分析(デュポンシステム)
- て)手元流動性比率(てもとりゅうどうせいひりつ)
- と)当座比率(とうざひりつ)
- と)投下資本(とうかしほん)
- の)のれん
- は)販管費率(はんかんひりつ)
- は)販売費(はんばいひ)
- は)配当性向(はいとうせいこう)
- ふ)フリーキャッシュフロー
- ふ)負債比率(ふさいひりつ)
- ま)マルチプル法(まるちぷるほう)
- り)流動資産(りゅうどうしさん)
- り)流動負債(りゅうどうふさい)
- り)流動負債比率(りゅうどうふさいひりつ)
- り)流動比率(りゅうどうひりつ)
- り)利益増加率(りえきぞうかりつ)
- れ)レバレッジ比率(ればれっじひりつ)
- ろ)労働分配率(ろうどうぶんぱいりつ)
- ろ)労働生産性(ろうどうせいさんせい)
まとめ
経営指標として使われるキーワード集です。詳細については別記事でひとつずつご紹介していきます。ご参考ください😃